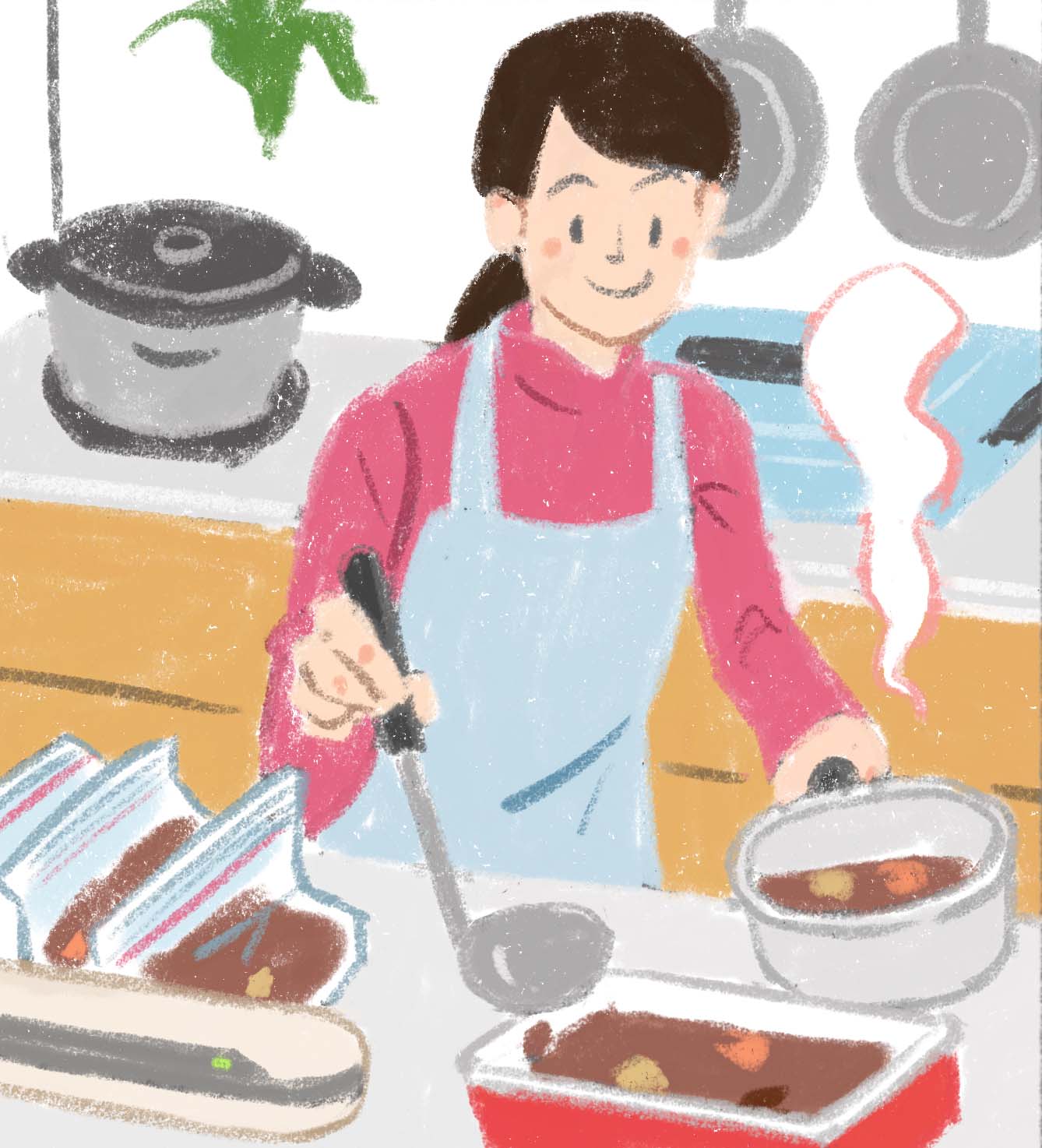縁を結ぶ、冠婚葬祭。セルモグループ
コラム 縁日和
コラム
COLUMN
セルモの代表を務める岩上梨可が、社長としてママとして書くコラム。
人と人の「縁」や、この国の人生儀式など、忘れてはいけない大切なことを綴っていきます。
主食である米が不足し2倍の価格に高騰する事態となった『令和の米騒動』。大変な社会問題だと感じると共に「食」について改めて考える機会ともなりました。これまで「台所にあるのが当たり前」だった食べ物の有り難さを多くの人が再認識したのではないでしょうか?
人は、食べてきたものでできています。何を、どんなふうに食べてきたのか。それは、体や健康を育むことはもちろん、その人の精神や、もっと言えば、私たちの文化をもつくってきました。お米は、その文字の成り立ちどおり「八十八」もの手間がかかっているという話を、昔の大人はよく口にしていました。「だから、最後の一粒まで大事に食べなさい」そんな躾を受けた人も多いはず。「もったいない」という日本人の精神文化を、いちばん分かりやすく伝えてきたのが「食」かも知れません。
「食」を考える時、大事なテーマとなるのが食事です。家族みんなが一緒に食卓を囲んでいた時代と違って、今は食事のスタイルも様々。忙しい若者の間では、”ながら“で食事が済ませられる「片手メシ」なる商品のニーズが高まっているという話も聞きます。私も「時短」は推奨派ですが、食事がそんな形ばかりになってしまうのは、それこそ「もったいない」ことだと感じます。
 食事をすることは、自分自身や共に食卓を囲む相手と向き合うことでもあります。どんなモノを美味しいと感じるか、食べっぷりはどうかなどを見ることで、自分や家族、対面する人のコンディションを感じ取ることができます。また、同じ物を食べながら何気ない会話を交わすことで、相手のことをより知ることができます。食事は、ただの栄養補給作業ではなく、自然なコミュニケーションをとる絶好の機会でもあると思うのです。
食事をすることは、自分自身や共に食卓を囲む相手と向き合うことでもあります。どんなモノを美味しいと感じるか、食べっぷりはどうかなどを見ることで、自分や家族、対面する人のコンディションを感じ取ることができます。また、同じ物を食べながら何気ない会話を交わすことで、相手のことをより知ることができます。食事は、ただの栄養補給作業ではなく、自然なコミュニケーションをとる絶好の機会でもあると思うのです。
一緒に食事ができない時でも、「食」は、家族や大切な人との繋がりをつくってくれる大事なツールになります。 例えば、お弁当。私は、子どもに初めてお弁当を作り始めた頃、幼稚園の先生から頂いたアドバイスをずっと大切にしています。それは、「可愛いキャラ弁も愛情表現としてはOK。でも栄養バランスが大事なので、とにかく海のモノと山のモノを両方入れてくださいね」というもの。子どものことを思いながら作るお弁当は、親の愛情を伝えると同時に子どもの体の成長を支えるもの。その意識を持つことが大切なことを教わりました。お魚を焼く時間がなければ、塩昆布やちりめん雑魚を添えるだけでも……と、忙しくてもひと工夫。そんな中で育ったからでしょうか、いま高校生の息子は、お店で買うおにぎりより私のおにぎりを食べたがります。「そういえば、私もお母さんのおにぎりの方が好きだったな」と自分を振り返り、当時の親の想いが分かる気がしています。
「いただきます」「ごちそうさま」、日本語には「食」への思いを表す美しい言葉があります。自然の恵み、いただいた命、そして、その一食のために注がれた人の手や愛情への感謝を込めた言葉。その精神こそ、「和食」がユネスコの無形文化遺産ともなったバックボーンではないでしょうか。冠婚葬祭をお手伝いする私たちセルモも、日本人が受け継いできた食の心を、お料理の中に少しでも盛り込み伝えていきたいと考えています。