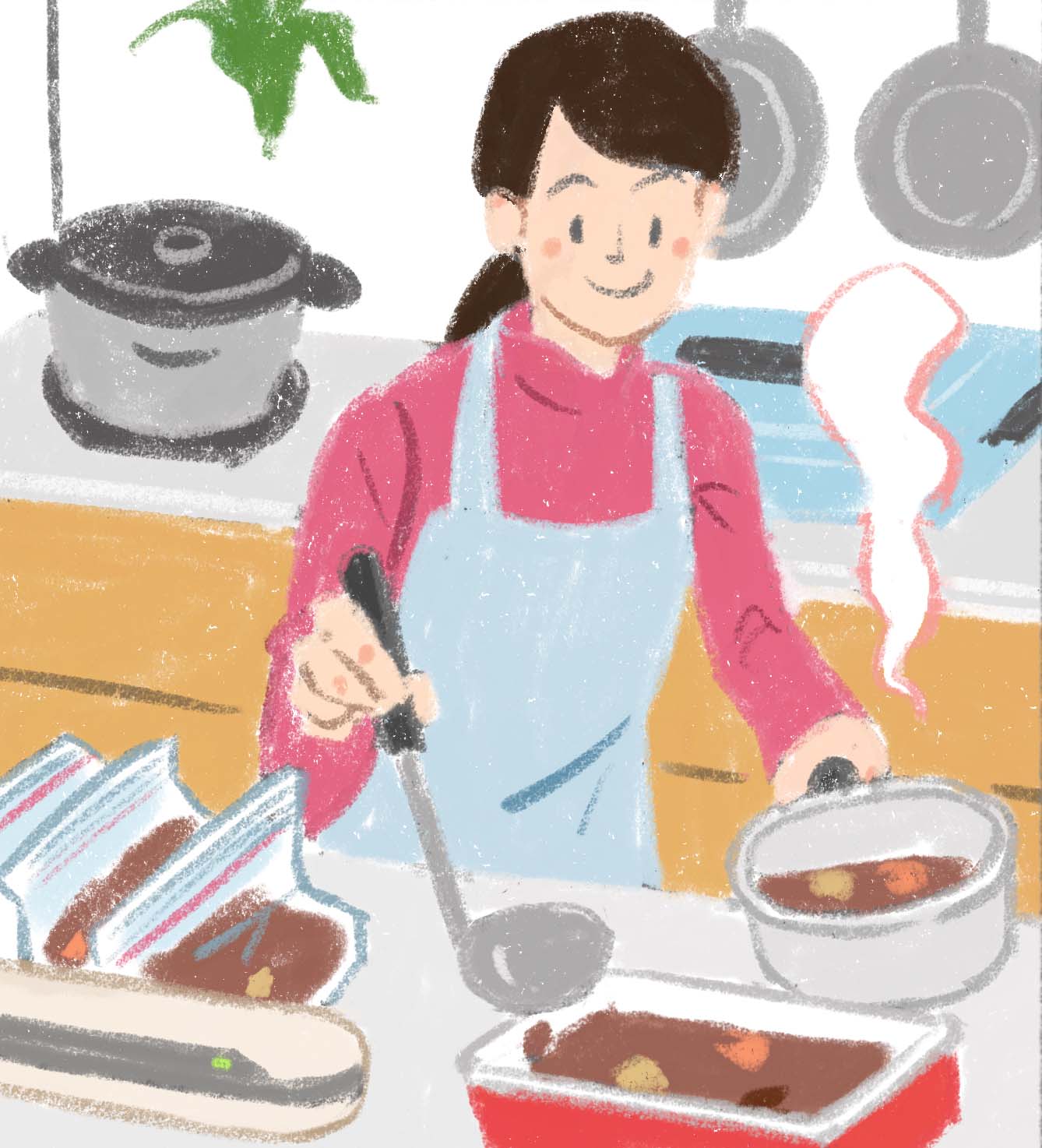縁を結ぶ、冠婚葬祭。セルモグループ
コラム 縁日和
コラム
COLUMN
セルモの代表を務める岩上梨可が、社長としてママとして書くコラム。
人と人の「縁」や、この国の人生儀式など、忘れてはいけない大切なことを綴っていきます。
いま経営者仲間の多くを悩ませている問題があります。それは、「〇〇ハラスメント」という表現があまりに安易に使われるようになったことで、通常の必要なコミュニケーションや人間関係の構築にまで支障をきたす場面が増えていることです。
そもそも「ハラスメント」とは、「嫌がらせ」のこと。相手に肉体的・精神的な苦痛を与え、人としての尊厳を傷つけたり権利を奪ったりすることを指します。上下関係のある社会や企業の中で特に問題になるのは、優位な立場にある人が、その優位性を利用して弱い立場の人に不当な要求をしたり人権を侵害したりする行為。もちろん、そんな行為は断固排除しなければならないし、受けた人は「NO!」を突きつけなければなりません。
ただ、「ハラスメント」と「自分にとって嫌なこと」とは違います。その線引きを間違えると、「ハラスメント」の誤認が生まれてしまいます。企業内で特にそれが生じやすいのが、教育です。上司は、部下に成長して欲しいし、育ってくれれば喜びもある。だから、相手のために良かれと思って声をかけたり、指導をしたりする。でも、これが、相手の感性や捉え方によっては「〇〇ハラスメントです!」と言われかねないことを恐れると、迷いや躊躇が生じます。また、受ける側も、経験値が少ないと「こんなことを言われた」と、表面的な事象だけに囚われて「これってハラスメントでは?」と思ってしまう。そうなると、未来ある人材が、本来乗り越えるべき壁に正面から向き合うことなく、成長の機会を逸してしまうのです。
 では、こんな事態を招かないためにはどうすればいいのか?必要なのは、両者ともに相手の真意を見極める努力をすることだと私は考えます。導く側は、率直なコミュニケーションを恐れない。「厳しいことを言うかも知れないけれど…」と、相手を気遣いつつも自分の本意をきちんと伝える努力をする。受ける側は、自分の価値観や好き嫌いだけで判断せず、相手が何を伝えようとしているのか、言葉の奥にある本質は何かを考える。また、周りの人たちも、相談に乗ったりサポートをするといった協力が必要です。
では、こんな事態を招かないためにはどうすればいいのか?必要なのは、両者ともに相手の真意を見極める努力をすることだと私は考えます。導く側は、率直なコミュニケーションを恐れない。「厳しいことを言うかも知れないけれど…」と、相手を気遣いつつも自分の本意をきちんと伝える努力をする。受ける側は、自分の価値観や好き嫌いだけで判断せず、相手が何を伝えようとしているのか、言葉の奥にある本質は何かを考える。また、周りの人たちも、相談に乗ったりサポートをするといった協力が必要です。
年齢も、育った環境も、個性も、感性も、何もかも違う人が集まっているのが社会。だから、誰もが耳障りのいいことばかり言ってくれるわけではないし、嫌なことにも遭遇します。でも、そんな中で、いろんな人に出会い、いろんな考えや価値観に接することで、人は、自分を成長させるものではないでしょうか。
「ウチの会社は厳しいですよ。でも、そんな中でも楽しみながら頑張りたい人は一緒にやりましょう!」私は、新卒向けの会社説明会でそう呼びかけることにしています。自社の社風や考え方をきちんと開示すれば、そこに賛同する若者が入って来てくれるからです。「多様性」という概念が一般化した今、人と人も、人と企業も、お互いにオープンな自己開示をすることが第一歩。その上で、違いを認め合い接点を見つける努力を惜しまないことが、ハッピーな社会をつくるベースになっていくのではないでしょうか。
私たちセルモの仕事は、人と人の絆を結ぶお手伝い。「ハラスメント」が闊歩する世の中ではなく、「人と人の繋がりって素晴らしい」そう感じる人が一人でも増える社会づくりのお役に立ちたいと考えています。